食品アレルギーとは |
| 臓 器 | 主な症状 | 主な疾患 |
| 全身 | 発熱、ショック | アナフィラキシー |
| 皮膚 | 掻痒(そうよう)、じん麻疹、湿疹 | アトピー性皮膚炎 |
| 眼 | 粘膜腫脹、掻痒(そうよう)、発赤 | アレルギー性結膜炎 |
| 消化器 | 口唇、舌、口腔粘膜腫脹 口蓋、咽頭の浮腫と掻痒 悪心、嘔吐、腹痛、下痢、下血 |
口角炎、口内炎 鉄欠乏性貧血、呼吸不良症候群 タンパク漏出性腸症 好酸球性腸炎、過敏性大腸炎 胃腸炎 |
| 呼吸器 | 咳、呼吸困難、鼻汁、鼻閉 くしゃみ |
気管支喘息 アレルギー性鼻炎 |
| 耳 | 耳漏 | 滲出性中耳炎 |
| 泌尿器 | 頻尿、血尿、タンパク尿 | 夜尿症、無症候性血尿 起立性タンパク尿 ネフローゼ症候群 |
| 神経系 | 頭痛、めまい 行動異常、性格変化 |
偏頭痛 アレルギー性緊張弛緩症候群 てんかん |
食品アレルギーの原因と食事療法 |
| 食品アレルギーの原因 |
| アレルギー反応は、「抗原」(アレルゲン)と呼ばれるアレルギーの素になるものを摂取することで起こります。(詳細は後述) 抗原が体内に入ると「抗体」ができ、そこへ再び抗原となるものを摂取すると、抗原と抗体が結びつき、「アレルギー反応」が 起こります。 抗原となりやすい食品成分は「タンパク質」です。しかし、タンパク質ですべての人がアレルギーを起こすわけではなく、起こ しやすい人と、そうでない人がいます。アレルギーになりやすい体質は、遺伝するといわれています。 . |
| タンパク質が「抗原」になるのはなぜか |
| タンパク質は「アミノ酸」がたくさんつながったものです。 食品のタンパク質は数個ずつのアミノ酸に分解されて吸収されます。普通は、アミノ酸が2~3個の状態まで分解して吸収 されます。この状態では、抗原にはなりにくいのです。 ところが、消化器官の消化力の未熟な(未発達な)乳幼児などでは、十分にタンパク質を分解できません。このため、アミノ 酸が10個程度つながったままの形で吸収されてしまい、アレルギーを起こしやすくなるといわれているのです。 . |
| アレルギー発生のメカニズム |
| ①食物、ダニ、カビなどのアレルゲン(抗原)が体内に入ると、「肥満細胞」(免疫に関係する細胞)が対応する。 ↓ ②体内に「抗体」(IgE)ができる。 ↓ ③抗体(IgE)が肥満細胞の表面に結合する。(肥満細胞は、「抗体に感作された」という) ↓ ④再びアレルゲン(抗原)が体内に入る。 ↓ ⑤④により、アレルギー反応が起こる。これを「抗原抗体反応」という。 ↓ ⑥⑤により、体内で化学伝達物質(ヒスタミンなど)が合成される。 ↓ ⑦化学伝達物質が体の各所でアレルギー反応を起こす。アレルギー反応の場所により、下記のような症状が出る。 *気管支:ぜんそく、鼻:アレルギー性鼻炎、目:アレルギー性結膜炎 皮膚:湿疹やアトピー性皮膚炎、消化器官:嘔吐や下痢 . |
| アレルギーの食事療法 |
| 食品アレルギーの「食事療法」は、主治医とよく相談し、原因となっている食物を特定し、それを除去する(摂取しない)こと になります。 先にも述べた通り、原因成分が成長や体力維持にとって重要な「タンパク質」であるため、間違った食事療法を行うと、特に 子供の場合は影響が大きいので、十分な注意が必要です。(代用食品の摂取などが重要) 近年、厚生労働省から出された新しい離乳食の基準では、食品アレルギー予防の観点から、アレルギーの原因となりやす い食品をあげて、一定の月齢まで与えないよう勧めています。いずれにしても、早期の対策が重要です。 . |
| 除去食のとり方 |
| 原因となる食品を除去するのが、食品アレルギーの食事療法です。 どの程度の除去を行うかは、アレルギーの症状や年齢、社会的な条件アドを考慮して決められます。完全な除去食で症状 がよくなっても、身体的、精神的負担が大きすぎると継続が困難になってしまいます。主治医とよく話し合い、必要最低限 の除去食にすることが大切です。 . アレルゲンとなる食品は卵、牛乳、大豆など、タンパク源として栄養的に優れたものが多いので、何もかも制限すると貧血や 栄養失調になる危険性があります。栄養のバランスを考え、上手に「代用食」(代わりの食品)を摂取することが重要です。 . .食品(食物)アレルギーは乳幼児期に多くみられ、成長とともに少なくなっていきます。ある調査では、生後6ヶ月の時点で 卵や牛乳のアレルギーがあった子供は、3歳になると過半数が、6歳になると8割近くが無症状になっているということです。 「除去食」の継続については、「3ヶ月ごと」に検討するのがよいとされています。 ただし、原因となる食品を食べてアレルギーが起こらなくなっても、しばらくは食べるのを控えめにしておくほうがよいようで す。 |
| 除去食の摂取方法の種類 | |
| 1. | 加工食品も含めて、アレルゲンを完全に除去 (タンパク質を酵素処理したり、アレルゲンを除去した「低アレルゲン食品」を摂る) |
| 2. | アレルゲンとなる食品そのものだけを除去 (加熱した食品や加工食品を摂る) |
| 3. | アレルゲンとなる同じ食品は続けて摂らず、一定の間隔をおいて食べる。 (牛乳は1週間に1回とするなど。これを「回転食」という) |
| 卵、牛乳、大豆がアレルゲンの場合の「代用食」 | ||
| 区 分 | 解 説 | 代用食品例 |
| 鶏卵アレルギー | 鶏卵および鶏肉を食事から除去します。うずらの卵や魚卵についても除去する必要が あるのかどうか、については、別途、調べる(検査する)必要があります。 マヨネーズや揚げ物の衣には卵が使われています。プリン、アイスクリーム、カステラ など、菓子類には卵が使われることが多いので、注意が必要です。 鶏肉で作ったスープの素、インスタントラーメン、ウインナー、ハム類、カマボコ、はんぺ ん、伊達巻、ちくわなどにもつなぎとして卵などが使われています。 . 【注】鶏卵アレルギーでも、鶏肉は食べられる場合もあります。 . |
・魚介類 ・豚肉 ・牛肉 ・大豆製品 ・卵を不使用の菓子類 . |
| 牛乳アレルギー | 乳製品(乳飲料、ヨーグルト、バター、チーズなど)と牛肉を食事から除去します。 マーガリンにも乳製品が混合してあるので、パーム油でできた「アレルギー用マーガ リン」を使用します。 インスタントのカレールウには、牛乳やバター、からあげ粉には脱脂粉乳が使われて いるので注意が必要です。また、菓子類には牛乳やバターが使われていることが多 いので、手作りされることをお勧めします。 パン類にもバターや脱脂粉乳が使われていますので、注意しましょう。 【注】牛乳アレルギーでも、牛肉は食べられる場合もあります。 . |
【カルシウムを補うもの】 ・ひじき ・ワカメ ・わかさぎ ・あみエビ ・しらす干し ・小松菜 ・大豆製品 ・牛乳を不使用の菓子類 |
| 大豆アレルギー | 大豆製品を食事から除去します。醤油の代わりには、小麦粉から作ったしょうゆ、魚 しょうゆ、ひえしょうゆ、あわしょうゆなどがあります。 味噌の代わりには、大麦から作られたみそを使います。 特に注意したいのは、油です。ほとんどの油に製造過程で微量の大豆油が含まれて います。米油、コーン油、なたね油、パーム油などを用い、微量混入を防ぐため、その 製品だけを製造しているメーカーのものを使うなどの注意が必要です。 . |
【醤油】 ・小麦粉しょうゆ ・魚しょうゆ ・ひえしょうゆ ・あわしょうゆ 【味噌】 ・大麦みそ 【油】 ・米油 ・コーン油 ・なたね油 ・パーム油 |
生活環境とアレルギー |
食べものとアレルギー |
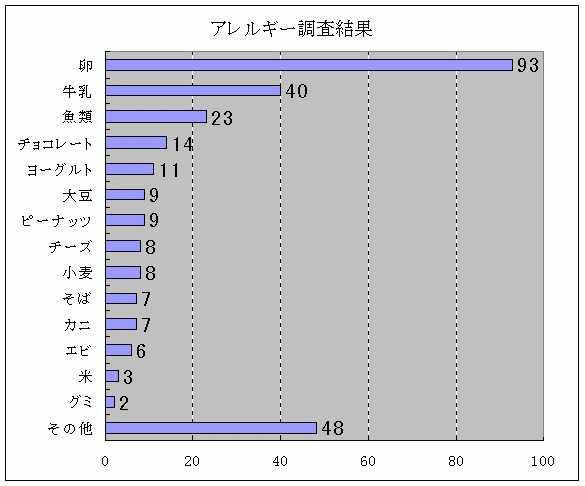
卵アレルギーの正体 |
| タンパク | 卵白タンパク質に 占める割合(%) |
分子量 | アレルゲン性 (テスト結果) |
| オボアルブミン | 54.0 | 45,000 | 3 |
| オボトランスフェリン | 12.0 | 76,600 | 2 |
| オボムコイド | 11.0 | 28,000 | 4 |
| オボムチン | 3.5 | 110,000 | 1 |
| リゾチーム | 3.4 | 14,307 | 3 |
| オボインヒビター | 1.5 | 49,000 | 1 |
| オボグリコプロテイン | 1.0 | 24,400 | 1 |
| オボフラボプロテイン | 0.8 | 32,000 | 1 |
アレルギーの種類 |
| 型 | 表現時間 | 関与する 細胞や物質 |
疾患の例 |
| Ⅰ型 (アナフィラキシー反応) |
即時型 | マスト(肥満)細胞 IgE 好塩基球 IgE |
・喘息(ぜんそく) ・じん麻疹 ・鼻炎 ・花粉症 ・アナフィラキシー ショック |
| Ⅱ型 (細胞融解反応) |
即時型 | IgM IgG 補体 |
・Rh不適合 ・自己免疫性溶血性貧血 ・薬剤アレルギー ・バセドー氏病 |
| Ⅲ型 (抗原・抗体複合反応) |
即時型 | 抗原・抗体複合体 補体・好中球 |
・全身性エリテマトーデス ・糸球体腎炎 ・薬疹の一部 ・食品アレルギーの一部 |
| Ⅳ型 (細胞性免疫反応) |
遅延型 | 感作リンパ球 リンホカイン |
・結核/真菌/ウイルス/その他の感染症 ・脊髄炎 ・脳炎 ・慢性関節リウマチ ・全身性エリテマトーデス ・薬物アレルギーの一部 ・同種移植片拒絶 |
食品アレルギーの検査 |
| 検査名/検査対象 | 検査方法 | どのようなときに実施するか | |
| 血 液 検 査 |
白血球 | 白血球の数を測定 | アレルギー性/非アレルギー性の鑑別 |
| 好酸球 | 好酸球の数を測定 | アレルギー性/非アレルギー性の鑑別 | |
| リスト法 | 血清中の総IgE抗体量を検出 | アレルギー性/非アレルギー性の鑑別 | |
| プリスト法 | 血清中の総IgE抗体量を検出 | アレルギー性/非アレルギー性の鑑別 | |
| ラスト法 | 特異的IgE抗体を検出 (5ランクに分けて判定) |
アレルゲンの特定 | |
| キャップ法 | 特異的IgE抗体を検出 (7ランクに分けて判定) |
アレルゲンの特定 | |
| エライザ法 | IgE抗体の総量、特異的IgE抗体、 IgG抗体、IgG4抗体の検出 |
アレルゲンの特定 (主に、研究の場で行われる検査) | |
| マスト法 | 総IgE抗体量、特異的IgE抗体、 IgG抗体、IgG4抗体、IgA抗体の検出 |
アレルゲンの特定 | |
| 細胞診 | 鼻粘膜や喀痰中の好酸球を調べる | アレルギー性/非アレルギー性の鑑別 | |
| 皮 膚 検 査 |
スクラッチテスト プリックテスト |
皮膚に傷をつけ、アレルゲンをたらして その後、反応を観察 |
アレルゲンを特定する際のスクリーニング |
| 皮内反応 | アレルゲンを注射して、その後、反応を 観察 |
アレルゲンの特定 (減感作療法で注射するアレルゲンエキス の量を決めるとき) | |
| パッチテスト | アレルゲンを皮膚にたらしてガーゼで 固定し、その後、反応を観察 |
遅延型アレルギーのアレルゲンの特定 | |
| 食物除去試験 食物負荷試験 |
特定の食品を一定期間除去したり、与 えて症状を観察 |
アレルゲンの特定 | |
| 誘発試験 | アレルゲンを吸入したり、鼻粘膜に貼っ たり、点眼して症状を観察 |
アレルゲンの確定診断 | |
| X線検査 | 胸部や副鼻腔のX線検査 | - | |
アレルゲン除去食とは |
食品添加物とアレルギー |
| 主な食品添加物 | |
| 用途別 の種類 |
概 要 |
| 着色料 | 食品を着色させるためのもの。 (最近では、クチナシ色素やパプリカ色素などの天然着色料が増加している) |
| 甘味料 | 食品に甘みをつけるためのもの。 |
| 香 料 | 食品に香りをつけるためのもの。 |
| 酸味料 | 食品に酸味をつけるために使われるほか、保存や酸化防止の機能も持っている。 |
| 保存料(防腐剤) | 食品に含まれるタンパク質や脂肪などを分解する微生物の働きや増殖を抑制して、 腐敗を防ぐ。 |
| 発色剤 | 食品のもつ色を鮮やかにするためのもので、ハムやソーセージに用いられている。 |
| 防カビ剤 | カビの繁殖や食品の腐敗を防ぐ効果がある。 |
| 殺菌料 | 保存料や防カビ剤は、細菌やカビの増殖を抑えるだけだが、この殺菌料は、その名 の通り、細菌などを殺すことができる。 |
| 酸化防止剤 | 食品が酸化して変質するのを防ぐためのもの。 |
| 膨張剤 | カステラなどを形よく焼き上げるために使用される。 |
| pH調整剤 | 食品の酸性度、アルカリ度を、ある一定の範囲内にとどめる効果がある。 |
| 前のページに戻る |